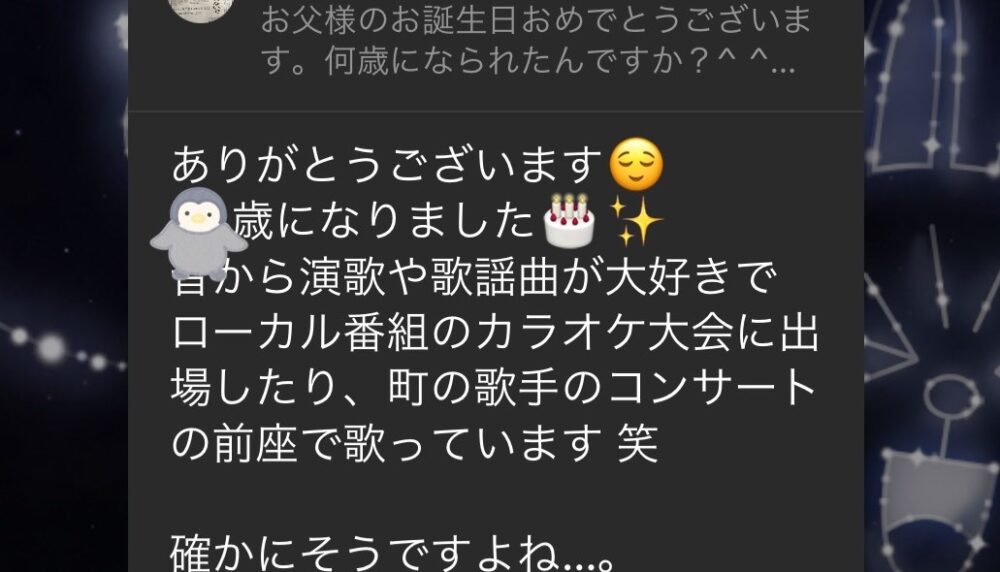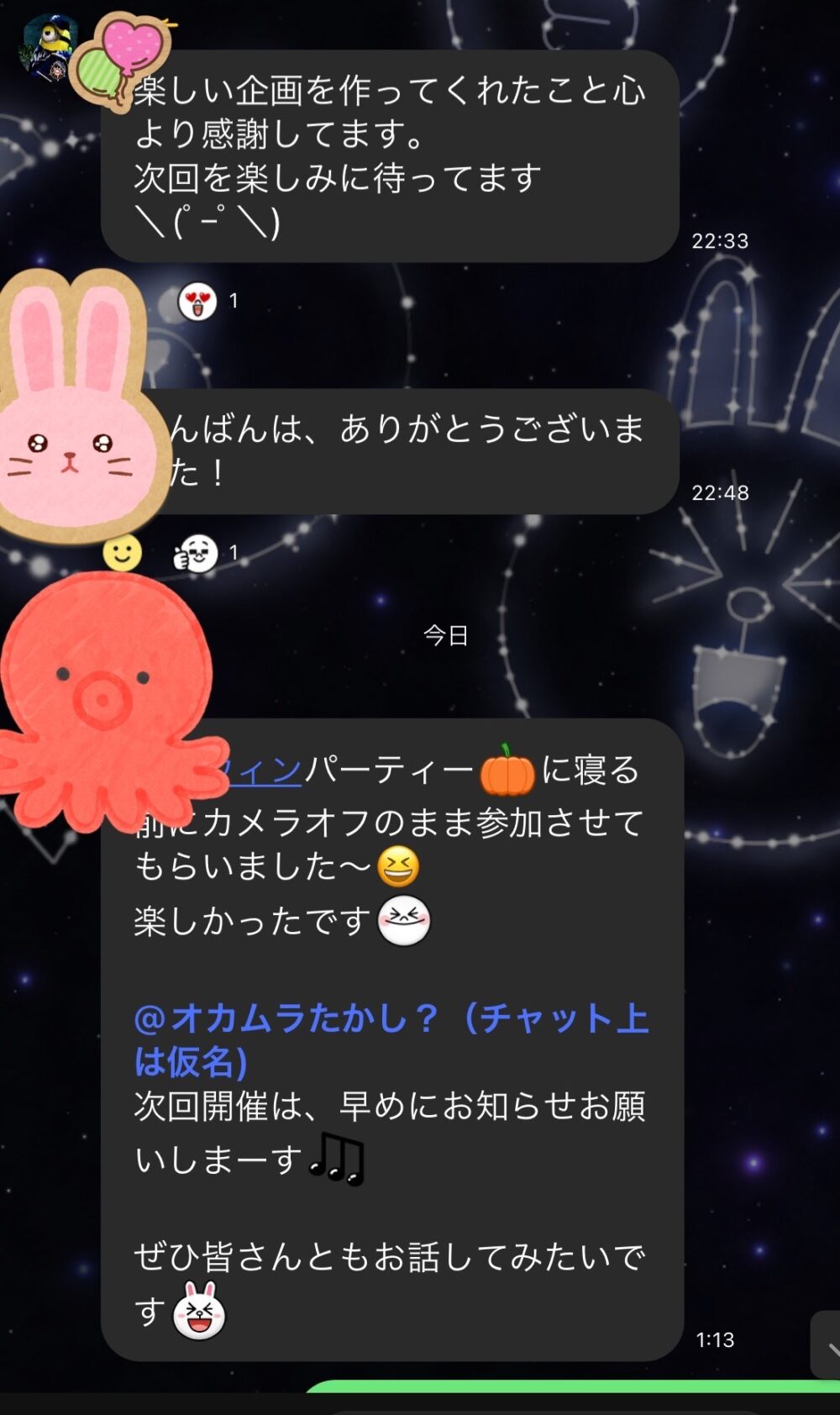「ケアラーやひきこもりなどいきづらさを抱えたひとたちの心のより度所」
2022年9月からLINEのオープンチャットで「デイリーLINEチャット」を開設しました。下記の要件にあてはまる方は、積極的に来てみてください。
厚生労働省で文部科学省と連携しヤングケアラーに関する調査研究の中で、「大人にしてほしいこと」は、「自由に使える時間がほしい」が男性で13.8%、女性で16.4%。「話を聞いてほしい」が女性で16.7%と上位。
また、若者ケアラー(全国の大学生が調査対象)でも「進路・就職と将来の相談にのってほしい」が28.3%、「自由な時間がほしい」が26.2%とトップです。
さらに、自殺対策の指針となる新たな「自殺総合対策大綱」をコロナ禍で年代別で見ると、「19歳以下」と「20代」の女性や小中高校生の自殺者が増えました。自殺者数は2020年は2万1081人(前年比912人増)で11年ぶりに増加している現状があります。若い人達が複合的な要因で一人で問題を抱え込み命を絶つのを少しでも減らす必要があります。
一方、40代のケアラーに目を転じると孤立しやすい状況になっています。総務省統計局の「平成29年就業構造基本調査」によれば、ヤングケアラーや若者ケアラーの人数54万人に比べ、89万5千人と35万5千人多くなっています。
しかも、就職氷河期世代で新卒から非正規雇用後介護離職し親や祖父母などを介護をする人たちも少なくありません。また、総務省の「介護施策に関する行政評価・監視 -高齢者を介護する家族介護者の負担軽減対策を中心として- <結果に基づく勧告>」によれば、介護後の就業状況は「正規の職員・従業員」は20.6%、「パートタイム・アルバイト」が 53.6%と正規職員の再就職が困難で貯蓄が少ない上に周囲と格差が生じるなどし孤立していきます。
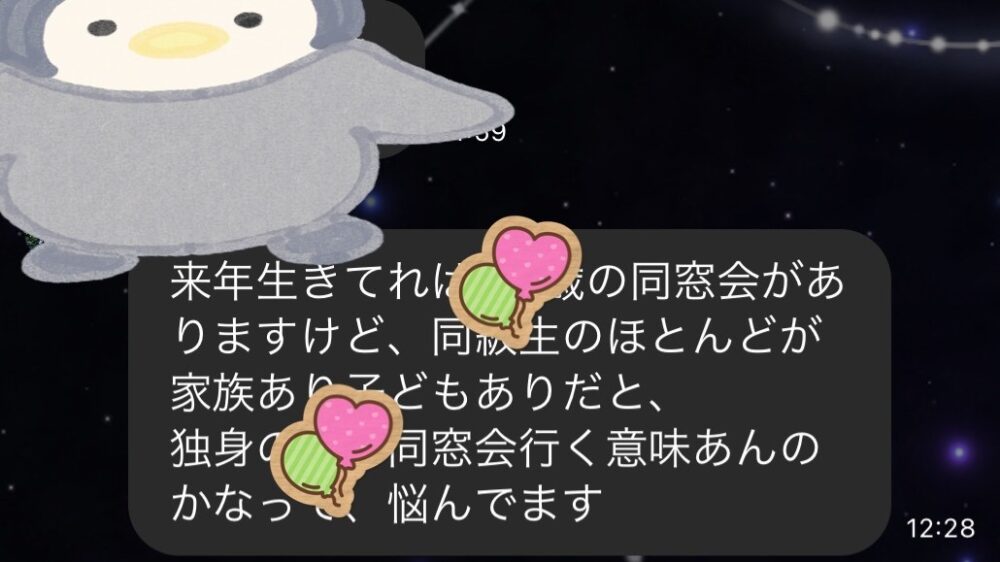
開設1か月半経過し、世代固有の悩みが明らかに
LINEのオープンチャットを開設し1か月半が経過しましたが、相談、悩み、雑談内容は多岐で固有の問題であるのがわかります。それぞれの世代に分けて、実際届けられた事例をベースに考えます。
ヤングケアラーの年齢に近い若者ケアラーは、「ケアの負担」より「家庭問題」が大半で、要介護者が「精神疾患」を罹患しているケースが多いです。
Aさん ひとり親家庭。要介護者より親が介護サービスを使うのは高いからあんたが面倒みてと無茶ぶりを言い続けられ、言いなりになり学生時代を過ごしています。
Bさん ひとり親家庭。母親が精神疾患、弟が重度の知的障害。学生時代からBさんが一人でケアを続ける。学業や部活がほぼできない状態な上、母親が精神科に通院せず頻繁に病院の付き添いがある。
若者ケアラーは、「家庭問題」に加え、「経済的に今、将来が不安」な人が目立ちます。年齢的に就職・恋愛・結婚・育児など人生のターニングポイントであり、お金がかかり出す年齢で無理もありません。現に20~30代のケアラーで将来に不安を抱える人は8割を超えているデータがあります。
Cさん 父親から「(働いているのに)生活費を出す余裕もないお前が母親の面倒を全部みてくれ」と言われ、長年、無業状態で生活費が底をつきフードバンクを依頼。
Dさん ひとり親家庭。二人兄弟。祖父母が認知症と脳出血でケアが必要になるものの、Dさんが精神疾患を罹患。親も生活困窮状態にあり、将来を悲観することもしばしば。
また、30代~40代のケアラー(ロスジェネ世代含む)のケアラーは、「ケアの負担が重い」、「経済的に困窮している」人が多い印象をもちます。
Eさん ひとり親家庭。アルツハイマー型認知症の親を1人で9年間介護し、介護途中に会社の理解が得られず介護離職。貯金を切り崩し、預金がほとんどなくなった。
Fさん ひとり親家庭。親が脳出血で後遺症、子どもが発達障害で介護と育児が重なるダブルケアを経験中。自営業で綱渡りの生活が続く。
「日頃からの密なコミュニケーションで一体感が生まれつつある」
「ヤングケアラー」や「若者ケアラー」は、子どもの頃から親の愛情を十分うけず虐待を受け続けて育った、親に祖父母のケアをおしつけられている、幼い頃に親が病気で死亡し、一人っ子で高校進学をあきらめ働きに出るなどさまざまな事情をもった人がいます。
ですから、大人に対して不信感を持ち続け「この人ほんまに相談できる人か」、「どうせ売名目的ちゃうん」とシビアで冷めた目や「この人は信用できる」となった後の依存心があっておかしくありません。あるいは、支援者がケアラーのバックグラウンドやヒアリングを十分に行わず怒ったり、注意したりすれば一気に関係性が崩れる場合があります。
このようなことから、支援者側もケアラーさんに対して、本気で向き合い接していく必要があります。
つまり、信頼関係を築くには、マンパワーに限界がありますが、日頃からの密なコミュニケーションが不可欠です。
開設1か月半が経過し、色々ありましたがメンバーの誰かが病気になれば、「大丈夫?」、「こういう方法があるよ」と相手を気遣うコメントが連投するようになってきました。
また、「今度、オンラインイベントやろうよ」とメンバーから自発的に声が飛び交うようになり、少しずつではありますが、一体感が生まれつつあります。
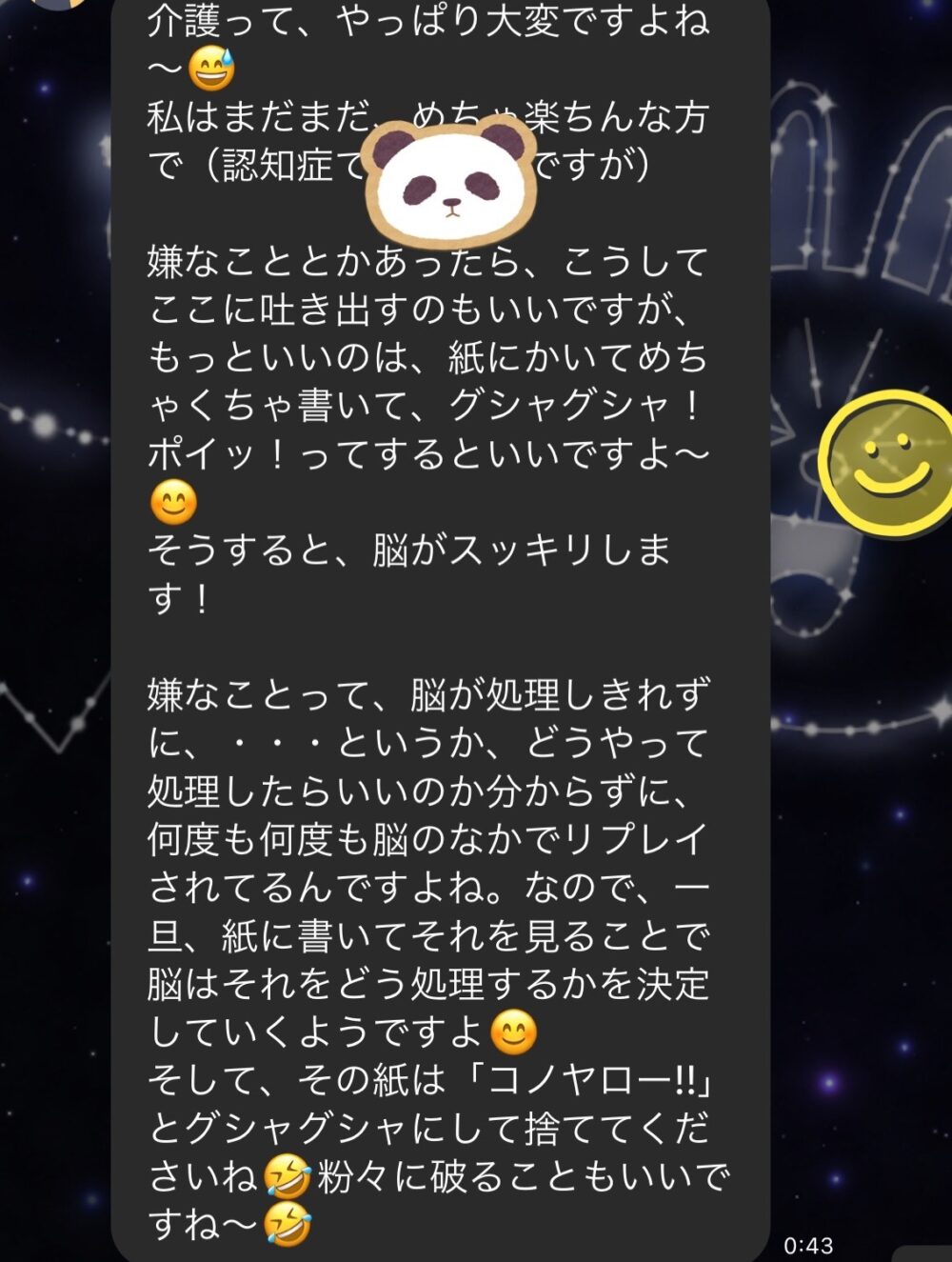
「ケアラーと家族それを支える人たちが一緒に悩み解決する共助空間を目指す」
このような問題に対して、私やケアラーと専門職(医療者・支援者・公認心理士・行政関係者・政治家・福祉関係の会社員)が共に悩みを解決のヒントをアドバイスします。また、介護の話ばかりでは湿っぽくなりがちなので、日常のたわいもない雑談や息抜き企画も大切にしています。共助のオンライン空間”やオンラインレスパイト空間を目指します。